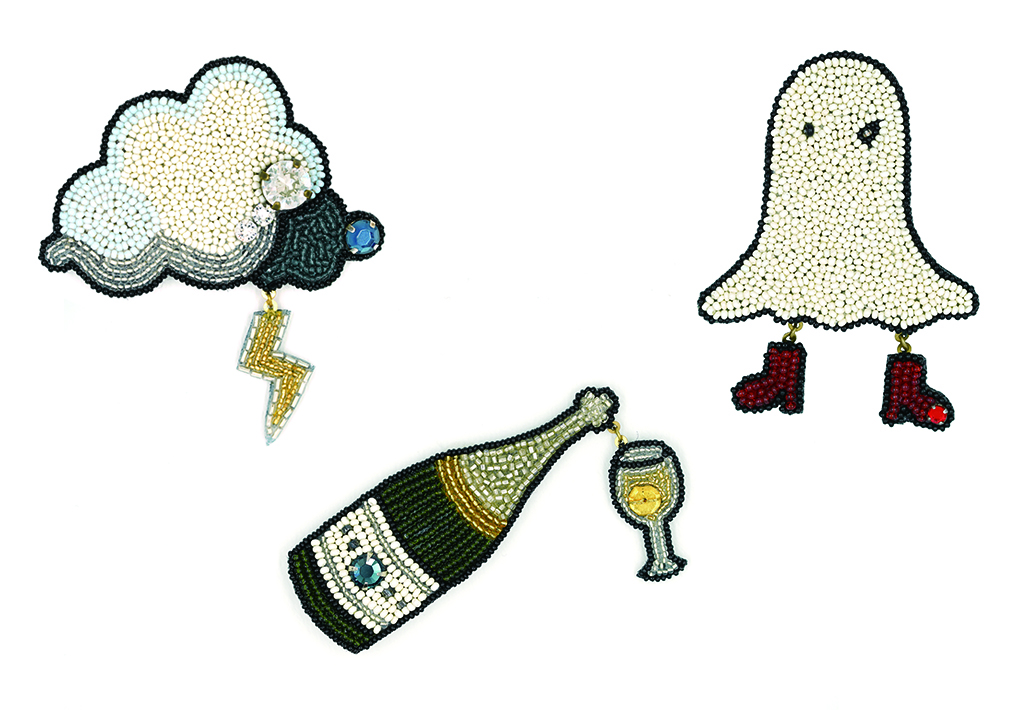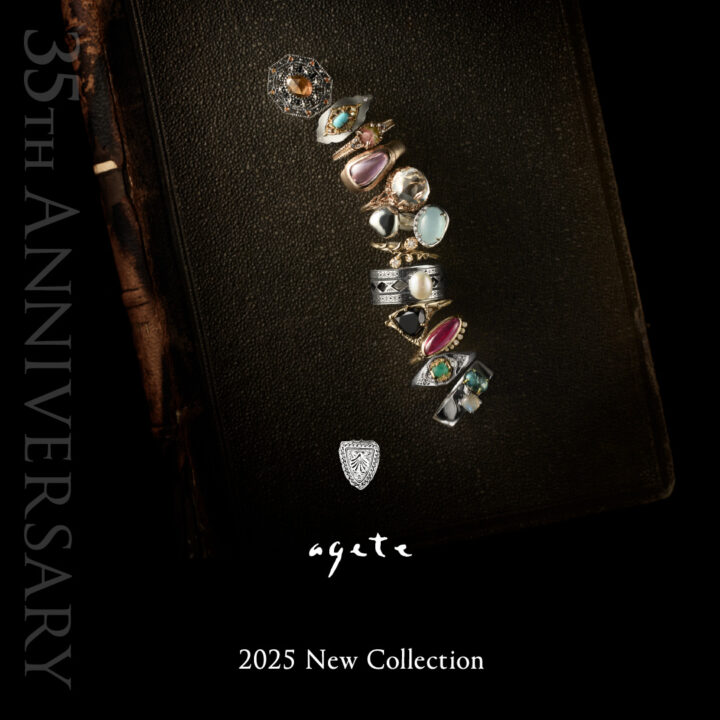『海外ビジネスで知りたい「ファッションロー」 スペシャルインタビュー』前編・中編に続き、後編では、海外でもブランドビジネスを継続し、持続していくために必要不可欠なポイントをお伝えします。
ブランドの周知(認知度)に関してのトピックや文化の盗用、気になる訴訟について解説してくださったのは近年注目が高まる「ファッションロー」に注力されている三村小松法律事務所の弁護士の方々です。
*前回までのインタビューはこちらをご覧ください
インタビュイー
小松隼也 弁護士、海老澤美幸 弁護士、新田真之介 弁護士(三村小松法律事務所)
目次
<前編>
1.「ブランドネーム(商標)」で注意すべきは?<中編>
2.「越境EC」を始める前に
3. 「著作権」と模倣の関係<後編>
4. 有名なデザインの基準をさがして
5.「文化の盗用」を掘り下げる
6.「訴訟」か、それ以外か?
5. 有名なデザインの基準をさがして
_「Maison Margiela(メゾン マルジェラ)」の「タビ」(シューズ)は世界的にも有名でもはや同ブランドの代名詞ですが、近年は他社商品のタビ風シューズをよく見かけます。日本の足袋メーカーがその形状を利用したシューズを製造していたりもします。そもそも足袋は日本固有の和装小物なので、ネガティブな印象は決してないものの、どこかモヤっとします。
小松隼也弁護士(以下、敬称略):
興味深いトピックですよね。「タビ」シューズの件はさておき、一般論として、ファッションデザインは、長期的に使われて広く認知されると、「周知」または「著名」なデザインとして保護される可能性があります。
具体的には、他の商品と明確に区別できるデザインで、かつ周知なデザインは、不正競争防止法2条1項1号・2号で保護されることになります。
_「周知」されているかどうかの基準はどこにあるのでしょうか。
小松:
売上や広告費、販売期間などが重要なポイントになるとされています。
面白いのは、雑誌やメディアなどにサンプルを貸し出してばんばん露出し、世間的には有名だったとしても、自身で広告費を投じていないと「周知」と認めてもらいにくいこと。
_広告費、ですか!
海老澤美幸弁護士(以下、敬称略):
そうです。例えば「Christian Louboutin(クリスチャン ルブタン)」のレッドソール。ルブタンが、似たようなレッドソールのハイヒールを販売する会社に対して、ルブタンのレッドソールを模倣していると主張して起こした裁判の中で、ルブタンのレッドソールが不正競争防止法2条1項1号で保護されるかが争われました。
一見、ルブタンは十分に「周知」であるように思われますが、この裁判では、第一審・控訴審ともにルブタンが負けています。特に第一審では、ルブタンのレッドソールが周知かどうかの判断の中で、ルブタンが雑誌編集者やスタイリスト、著名人などからの要望や依頼に応じて、雑誌の記事、メディアでの撮影などに使用するためにルブタンの商品を貸し出すという広告宣伝方法を行うだけにとどまり、自ら広告宣伝費用を払ってテレビや雑誌、ネットなどの広告宣伝を十分に行っていないという事情も考慮され、周知ではないと判断されています。
このように、現在の法律では、周知かどうかの判断では掛けた広告費がポイントの一つになるんです。
_SNSでのバズりはどう扱われますか?
小松:
SNSでも広告費をかけていれば認められますが、ハッシュタグなどでバズったとしても広告の扱いにはならず、裁判所は重視しないと思います。つまり、広告費をかけられる大企業が有利ということになりますね。
6.「文化の盗用」を掘り下げる
_これまで海外を視野に入れたビジネス展開を中心にお話を伺いましたが、それとは別に最近気になる文化の盗用に関して質問です。その土地固有のモチーフやデザインなどを商品デザインに使用すること自体はよく見受けられますが、法的には問題ないのでしょうか?
新田真之介弁護士(以下、敬称略):
基本的には問題ないでしょう。ただ、近年は文化の盗用に対抗するため、自国の文化を法律で保護する動きもあります。
例えばメキシコでは、先住民族発祥の知的財産を保護するための法律ができました。メキシコの伝統的なモチーフなどを使用した商品を販売した場合、メキシコ政府からブランドに対して警告書が届く可能性はあります。

海老澤:
実際、メキシコ文化省は、「Isabel Marant Étoile(イザベル マラン エトワール)」や「ZARA(ザラ)」、「Levi’s(リーバイス)」などがメキシコの伝統的な模様や刺繍などを使用したことが「文化の盗用」に当たるとして書簡を送付していますね。
文化の盗用について世界的な定義があるわけではありませんが、個人的には、マジョリティがマイノリティの文化を、マイノリティの関与なく/誤解した文脈で/文化への敬意なく、自社の利益を上げる目的で私物化することと考えています。
過去に、キム・カーダシアンさんが「KIMONO」を商標登録し、ビジネスとして展開しようとしましたが、それは「文化の盗用」との批判を免れないと思います。
このように現在では、利益の搾取があるかどうかを「文化の盗用」の重要な要素と考えるのが主流だと思います。
新田:
利益の搾取でなければ、個人的にはアリだと思うんですよね。ちゃんとリサーチして表現の手段として用いられるのであれば。でもそれが盗用された方の感情を害してしまったり、利益の搾取に捉えられると炎上する。
海老澤:
特にファッション業界では、民族の柄やモチーフなどを特に深く考えずに「かわいい」という感覚で取り入れてきたケースも多いのではないでしょうか。フリーライドのように表面だけを取り入れて利益を上げることへの嫌悪感が批判の対象になっているのではないかと思います。
最近では、世界で「文化の盗用」を規制する動きもあります。その文化について十分リサーチして理解を深め、なぜその文化を取り入れるのか、どうしてこのデザインにするのかなどをきちんと説明できるよう準備しておくことが重要だと思います。その文化に対して敬意をもって真摯に取り組むことが大切ですね。
小松:
ちょっとかっこいいと思ったんだよね〜くらいじゃダメ笑
海老澤:
ほんとその通り!

7.「訴訟」か、それ以外か?
_さまざまなアドバイスを伺いましたが、それでも…というときのためにお伺いします。実際のご相談で、訴訟になる事案はどのくらいあるのでしょうか?
海老澤:
かなり少ないです。例えばデザイン模倣のケースの場合、権利者から「不正競争防止法2条1項3号違反だから、商品の販売中止と損害賠償を請求する」といった内容の警告書が届き、そこから当事者間の任意の話し合いで解決することが大多数だと思います。
訴訟は、起こす側にとっても起こされる側にとっても時間とお金がかかるので、任意の話し合いの中で解決しようというインセンティブが働きやすいんですよね。模倣事案の裁判の結果がニュースで報じられることがありますが、これはごくごくわずかな事例ということになります。
新田:
訴訟は公開されますし、判決が出るまでの間にブランドイメージに傷もつきますから。また、もし裁判を起こしたものの、「このデザインは法律上保護されない」という判決が出てしまったら、パクリ放題になってしまうという懸念もあります。
_そうなのですね!訴訟は日常茶飯事かと思っていました。
小松:
そもそも「ファッションロー」は、アメリカで確立された法律分野です。アメリカはご存知のように契約文化で訴訟大国ですから、アメリカでは訴訟は日常茶飯事です。
海老澤:
個人的な感覚ですが、アメリカは業界の利益を守るという意識が発達しているように思います。ファッションロー以外にも、例えばカリフォルニアでは「ワインロー」という分野もあると聞いたことがあります。
実は、ファッションローが登場した背景には、科学技術の発達、ファストファッションの台頭、コングロマリットの登場の3つがあるといわれています。つまり、技術が発達して模倣品が増える中で、大企業の市場での発言権が強まったことがファッションローにつながったということですね。このように、ファッションローは模倣品排除を契機としています。

小松:
昨今は日本でも「アートロー」や「デザインロー」などクリエイティブに関する法律整備が盛んになってきました。ジュエリーは、ファッションとは違う商習慣があります。日本はジュエリーの取引量と売上高が多いので、事案が発生する機会も多いのではないでしょうか。
そういう意味では、ジュエリー業界では法への関心は高いのではないかと思います。他方で、契約文化はそこまで浸透していないとも感じています。
新田:
ジュエリーはファッションに比べて商品として息が長い。また、一度ヒットすると長く売れ続けるのは日本市場の傾向でもあります。素材自体が金融価値を持っていますし、ファッション性のみならず工芸的な要素もあり、アート性も高いです。
その点に鑑みても、意匠登録を含め、もっとデザインの保護を意識すべきだと思います。ブランドを立ち上げたり、事業拡大を考えていらっしゃる方は、ぜひ早い段階でブランドを守る武器を携えておいた方が良いでしょう。
海老澤:
このようにデザインにはさまざまな法律や権利が関わってくることを知っていただくことが、クリエイティブにはとても重要だと思っています。そして、クリエイティブを自由にすることが、ファッションローの一つの目的だと考えています。
前編から3部に分けて海外ビジネスの際に知りたいファッションローに関する実践的な知識や具体例をお届けしました。いかがでしたでしょうか。
法は問題が起きてから解決するための手段だけではなく、自分たちを守るためにも身につけておく知識ということがよくわかりました。
また、何より、最後の海老澤先生の「クリエイティブを自由にすることがファッションローの目的」という言葉が本質かと思います。表現したいこと、使ってもらいたいデザイン、売りたい商品を世の中に出す前に懸念事項を洗い出し、クリアにしておくことは、今の時代においてその後のブランドビジネスの羽ばたきを考える上でなくてはならない作業ですし、望まないことで他者と揉め続けるよりは、法に則り解決に向かう方が次のクリエイションに進めるからです。
ファッションローについてお話を伺った3名の先生方は、弁護士という職業ながらカウンセラーに近いと感じました。クライアントの声を聞き適切な対処を考え、寄り添ってくれるような存在です。
法律事務所と聞くと敷居が高いイメージですが、なんとなく気になることがあった時点で、気軽にコンタクトを取れる=話を聞いてくれる味方がいることはとても心強いのではないでしょうか。法を身近に感じさせてくれるお話を、ありがとうございました。
三村小松法律事務所
三村小松法律事務所ではファッション・ジュエリー業界で必須な「ファッションロー」を注力分野の一つに掲げ、海老澤美幸弁護士を中心に「ファッションロー・ユニット」を立ち上げました。デザインに関するご相談のみならず、取引先との契約、労務(フリーランスとの契約など)、ステマ、賃貸借契約(定期賃貸借などの条件交渉、内装)、カスハラなど、小売に関わる幅広いご相談を受け付けています。弁護士へ相談というとハードルが高いイメージですが、スポットでのご相談を受け付けており、顧問契約いただいた方からの問い合わせはLINEでもOKとのこと。詳細は公式サイトをご覧ください。