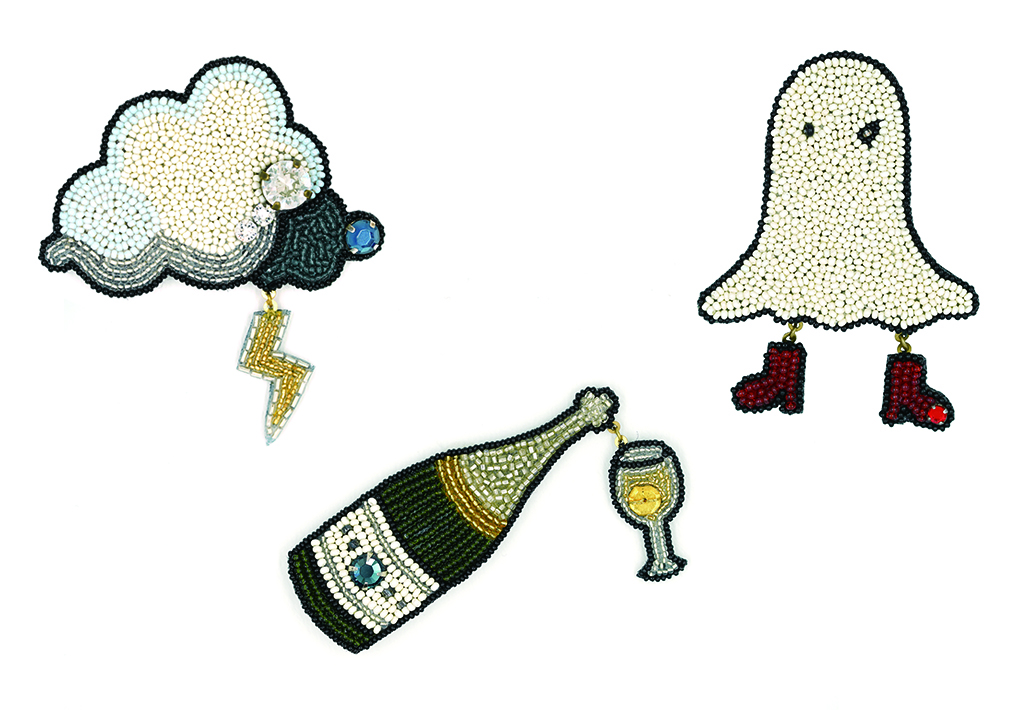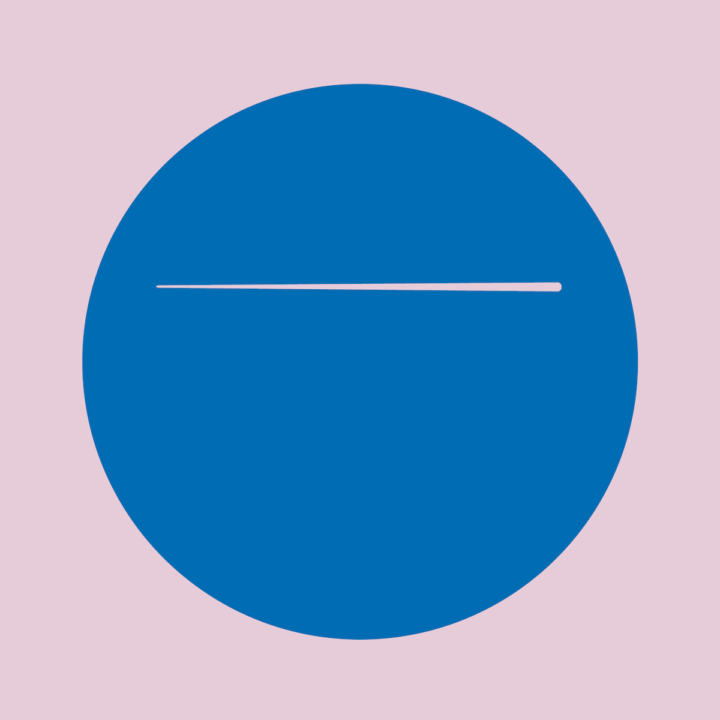ファッションやジュエリー業界ではここ数年、POP UPショップや越境ECサイトなどを含め海外進出の機運が高まっています。
うまくビジネス展開するためにここで押さえるべきポイントは、自国と相手国の法理解。商習慣のみならず、ビジネスに関する法律は国ごとに違い、その点を理解しておかないとトラブルや商機会を失う事態になりがちです。
本インタビューでは、海外展開も視野に入れたブランドビジネスを継続し、拡大していくために必要不可欠なポイントを前・中・後編にわたりお伝えします。 解説してくださったのは近年注目が高まる「ファッションロー」に注力されている三村小松法律事務所の弁護士の方々。JEWELRY JOURNALが2021に掲載したインタビューと合わせてお読みください。
インタビュイー
小松隼也 弁護士、海老澤美幸 弁護士、新田真之介 弁護士(三村小松法律事務所)
目次
<前編>
1.「ブランドネーム(商標)」で注意すべきは?<中編>
2.「越境EC」を始める前に
3. 歯がゆい「模倣」<後編>
4. 有名なデザインの基準をさがして
5.「文化の盗用」を掘り下げる
6.「訴訟」か、それ以外か?
1.「ブランドネーム(商標)」で注意すべきは?
小松隼也 弁護士(以下、敬称略):
この5年で数多くの相談を受けましたが、最近多いのは「海外でビジネス展開する際のブランドネーム(商標)」についてです。
基本的な話ですが、ブランドネームは、そのブランドネームを使う商品やサービスとセットで商標登録すれば商標権で保護されます。もし自社ブランドと同じネーム(商標)がすでに同じ商品やサービスで登録されている場合、そのまま自社ブランドネームを使用すると商標権侵害として権利者からクレームを受ける可能性があります。
商標権侵害に当たれば、小売店やサイトなどで商品を扱ってもらえなくなります。これは国内に限った話ではなく、海外でも同様です。
_期間限定のポップアップでも注意すべきでしょうか?
小松:
はい。商標権侵害に当たるかどうかに期間は関係ありませんので、たとえ短期間のポップアップでも商標権侵害になります。
ですから、取り扱い先の国ごとに、商標登録されていないかを確認することが必要です。そして、できれば自社ブランドのネームやロゴなどを予め商標登録しておくことが重要になります。
取り引きが決まりそうな際に急いで商標登録しようとしても、登録可能かが分かるまで時間がかかり、ローンチのタイミングまでに間に合わない場合も出てきます。
_取引を予定している相手国で商標登録をしていないと、展開を諦めるほかはないのでしょうか?
海老澤美幸弁護士(以下、敬称略):
ここは混乱しやすいのですが、海外で商標登録していなくても、ブランドネームを使用すること自体は可能です。
ただ、別のブランドが同じ・似たブランドネームを先にその国で商標登録している場合、相手ブランドの権利を侵害することになりますので、そのブランドから商品の販売の中止や損害賠償を請求される可能性があります。このため、特に海外取引先と取引する場合の契約書には「商標の使用に問題がないことを保証する」という条件がほぼ必ず明記されています。
_商品を取り扱ってくれる卸先やポップアップ先の小売店にも影響があるのでしょうか。
海老澤:
例えばブランドが海外の百貨店に商品を卸すケースでは、そのブランド名が誰かの商標権を侵害している場合、ブランドはもちろん、その商品を販売する百貨店側も商標権侵害として責任を問われることになります。
こうしたリスクを避けるため、保証するという条件が明記されているわけです。さらに進んで、取引先から、その国で商標登録していることまで求められることもあります。 このように、相手国で商標登録できていないことを理由に展開をあきらめざるを得ないことは少なくありません。
_商標登録までの期間や金額を教えてください?
小松:
海外の商標の出願は早ければ2週間くらいで対応が可能です。国によって異なりますが、1カ国約30万~50万円、登録後の有効期間はおおむね10年間かと思います。
ただ、日本では登録できたブランドネームが、海外ではできないというケースは少なくありません。海外展開を視野に入れている場合は、ブランドネームを決める段階から、法律の専門家にどのようなブランドネームがよいかを相談することが重要です。
海老澤:
例えば、英語の一般的な名称をブランド名にした場合、日本では商標登録できても、アメリカでは一般的な名称だからという理由で商標登録不可能な場合もあります。
それでもアメリカで登録したいという場合は、ブランドネームを変えなければなりません。それは、ブランドにとっても本意ではないですよね。

小松:
そうした理由で元のブランドネームでの海外展開を諦めたブランドを数多く見てきました。
ですので、ブランドネームを決めてから「これは登録できますか?」と聞くより、決定の前段階から専門家と一緒に考える方が効率的。海外展開しにくい名前やその国ごとのルールを伝え、共に練り上げていくことができます。
_最近は普遍的な英単語や頭文字のアルファベットだけ並べたブランドネームをよく見かけます。かぶることもありそうですよね。
小松:
近年はシンプルな商標がキャッチーで人気がありますが、先にお伝えした通り、その国では一般的な名称すぎて登録できないか、シンプルすぎて既に誰かが登録している可能性も高い。日本のアパレルブランドなどのブランドネームを決める際もその点を鑑みながら関わらせてもらっています。
新田真之介 弁護士(以下、敬称略):
ジュエリーや宝飾系業界では、過去には商標登録の類似性という点において高級宝飾時計ブランドの「FRANK MULLER(フランク ミュラー)」と「フランク三浦」の事件がありました。
海老澤:
これは、先に「FRANK MULLER」が商標登録されており、「フランク三浦」が商標登録できるかどうかが争われた事件でした。
ブランドネームが似ているかどうかは、「称呼(呼び方)」「外観(見た目)」「観念(そのブランドネームから受けるイメージ)」などを全体的に考察して、さらに取引の実情を考慮し、誤認混同が起こるおそれがあるかどうかで判断するとされています。 「FRANK MULLER」と「フランク三浦」が似ているかについて、特許庁と一審の東京地裁は似ていると判断しましたが、知財高裁は似ていないと判断し、「フランク三浦」の商標登録を認めました。
_知的財産の観点からは似ていないという判断がされたのですね。
小松:
「FRANK MULLER」と「フランク三浦」の場合は、呼称は似ているけれど、外観と観念が当てはまらなかったのではと。その辺りを総合的に判断して似ていないということになったのではと思います。
新田:
たしかに「FRANK MULLER」の時計を買いたい人が間違って「フランク三浦」を買うようなことがあり得るかというと、「誤認混同するおそれはない」という感覚の方が多いでしょう。その意味では、「FRANK MULLER」側敗訴の結論も理解できるのですが、この結論に関しては原告のブランドイメージを損なうような効果があることも無視できないのではないか、と批判する専門家もいますね。

_商標登録について専門家のアドバイスが大切なことはよく分かりましたが、素人でも調べられるデータベースがありそうですが。
海老澤:
商標登録や出願状況について調べられる検索データベースはあります。 一般の方でも検索できますが、調べ方にはコツが必要です。また、国によってはデータベースの精度に問題があり、100%安心とは言えません。
AIを利用した登録サービスなどもあるようですが、最後のチェックはどうしても人(専門家)の手を介さないと不安が残ります。
小松:
我々は主要国の現地事務所とほぼ提携できているので、その点を精巧に調べられるのは強みだと感じています。
特に海外展開を考える場合、「商標権」については知っているつもりでも盲点が多いことがよくわかりました。ブランド名を決める際には、躊躇せず先手を打つことが必要かもしれません。
「海外ビジネスで知りたい『ファッションロー』 スペシャルインタビュー」中編では、ブランドやセレクトショップのみならず百貨店も本腰を入れて取り組み始めている「越境EC」と、発見した場合の心理的ダメージも大きい「模倣」についてお届けします。
三村小松法律事務所
三村小松法律事務所ではファッション・ジュエリー業界で必須な「ファッションロー」を注力分野の一つに掲げ、海老澤美幸弁護士を中心に「ファッションロー・ユニット」を立ち上げました。デザインに関するご相談のみならず、取引先との契約、労務(フリーランスとの契約など)、ステマ、賃貸借契約(定期賃貸借などの条件交渉、内装)、カスハラなど、小売に関わる幅広いご相談を受け付けています。弁護士へ相談というとハードルが高いイメージですが、スポットでのご相談を受け付けており、顧問契約いただいた方からの問い合わせはLINEでもOKとのこと。詳細は公式サイトをご覧ください。